脳血管内科
研究紹介
1. 脳血管内科とは
脳血管内科は、1977年の国循開設時に山口武典初代部長(現名誉総長)によって開かれた診療科で、二代目の峰松一夫部長時代(1995年~2016年より病院長、現名誉院長)、三代目の豊田一則部長時代(2010年〜2017年、現副院長)を経て、現在に至っています。この間、一貫して脳血管障害の診断と治療に力を注ぎ、とくに脳卒中急性期の内科治療法の開発に努めてきました。
脳血管内科は脳血管障害を全身血管病として捉え、神経病学・循環器病学・救急医学・血栓止血学・画像診断学・リハビリテーション医学などの多角的な視点から診療と研究活動を進めています。豊富な入院患者の綿密なデータベースに基づいて、脳血管障害の症候学・病態生理・診断・内科治療などを解明する多くの研究を、連綿と発表し続けてきました。その活動実績を国内外で評価され、近年では脳血管障害研究の国際的中核機関と位置づけられるようになりました。厚生労働省や日本脳卒中学会、日本脳卒中協会などの関連学術団体等と連携を密に取りながら、全国多施設と共同して大型臨床研究を主宰する機会も増えています。とくに急性期脳梗塞患者へのrt-PA静注療法の国内承認および承認後の全国規模の調査・研究で国内の諸施設を牽引し(J-ACT, J-ACT II, MELT-Japan, J-MARS, SAMURAI,BAT2, THAWS , THAWS2, T-FLABORなど)、近年の脳卒中急性期内科治療の発展に寄与する研究活動を続けています。海外からも国際共同臨床試験への参加を要請され、国内多施設共同での国際試験の実現に努めています(ATACH-II, EXTEND,FASTEST,ELANなど)。研究所やセンター外研究施設と連携したトランスレーショナル・リサーチの推進にも力を入れ、頭蓋内動脈解離、脳出血、原因不明脳梗塞・ESUSの遺伝学的研究などを行っています。
また、脳血管内科は脳卒中内科診療の担い手を多く養成する使命を帯び、それを実践してきました。歴代スタッフ・修練医が全国の第一線施設で活躍し、脳卒中診療の大きなネットワークを形成しています。現在も多くの専門修練医・レジデントが、最新診療技術の習得と夢のある臨床研究に励んでいます。
脳血管内科は、わが国の国民病である脳卒中の征圧を目指して、内外のパートナーと連携しながら診療・研究・若手の育成を進めています。
2. 当科が取り組むプロジェクト
(最近10年間に主宰した多施設共同研究より)
1. SAMURAI研究

The Stroke Acute Management with Urgent Risk-factor Assessment and Improvement Study
| 公式名称 | 厚生労働科学研究: わが国における脳卒中再発予防のための急性期内科治療戦略の確立に関する研究 |
|---|---|
| 主任研究者 | 豊田 一則 |
| 事務局 | 古賀 政利、吉村 壮平、井上 学、田中 寛大、塩澤 真之 |
| 研究内容のご紹介 | http://samurai.stroke-ncvc.jp SAMURAI研究を欧州、豪州、韓国など多くの国際共同研究に登録しさらなる研究成果を発信しています。 |
| 研究概要 | SAMURAI研究の紹介ページ |
2. ATACH II研究
| 公式名称 | Antihypertensive Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage-II、米国NIH助成 (ClinicalTrials.gov number, NCT01176565; UMIN000006526) |
|---|---|
| 主任研究者 | 豊田 一則(日本側研究者代表) |
| 事務局 | 古賀 政利、福田 真弓、三輪 佳織、田中 寛大 |
| 研究内容のご紹介 | ATACH2データを使用したサブ解析研究も行っています。 |
3. THAWS・THAWS2研究
 THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset Strokes Trial
THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset Strokes Trial
| 公式名称 | 睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安全性に関する臨床試験 |
|---|---|
| 主任研究者 | 豊田 一則 |
| 事務局 | 古賀 政利、井上 学、吉村 壮平、三輪 佳織、福田 真弓 |
| 研究内容のご紹介 | これまでアルテプラーゼ静注療法の対象とならないことが多かった、起床時発症脳梗塞や発症時刻不明脳梗塞患者のうち頭部MRI検査所見で発症から数時間以内である可能性が高い患者に対して同療法の効果を調べる研究です。THAWSでアルテプラーゼ0.9mg/kgによる本療法が安全であることを確認しました。現在、THAWS2研究を行い、観察研究で実臨床における本療法の安全性と有効性を確認する予定です。 http://thaws.stroke-ncvc.jp/ |
4. BAT2研究

| 公式名称 | 日本医療研究開発機構(AMED)研究事業 脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と安全性の解明 The Bleeding with Antithrombotic Therapy Study 2 |
|---|---|
| 研究代表者 | 豊田 一則 |
| 事務局 | 三輪 佳織、田中 寛大、吉村壮平 |
| 研究内容のご紹介 | 抗血栓療法新時代において、脳血管障害を中心とした循環器疾患患者への経口抗血栓薬(抗血小板薬・抗凝固薬)の使用実態と安全性を解明するため、全国から5367例を登録しました。観察期間は2年間であり、2021年3月まで追跡調査を行います。 http://bat2.stroke-ncvc.jp |
5. FASTEST

| 公式名称 | 脳出血超急性期患者への遺伝子組換え活性型第Ⅶ因子投与の有効性と安全性を検証する研究者主導国際臨床試験(rFVIIa for Acute Hemorrhagic Stroke Administered at Earliest Time:FASTEST) |
|---|---|
| 研究代表者 | 豊田 一則 |
| 事務局 | 古賀 政利、井上 学、吉村 壮平、三輪 佳織、福田 真弓 |
| 研究内容のご紹介 | 脳出血は、日本国内において年間4~5万人程度に発症すると推測されます。脳梗塞が近年の急性期再開通治療(tPA静注、機械的血栓回収)の進歩などで「治せる病気」になった一方で、急性期脳出血には決定的な治療法がありません。このため脳出血は死亡や高度機能障害に繋がり易く、征圧が切望される国民病です。 この度我々は米国、カナダ、欧州の研究者らと共同で、発症早期の脳出血患者さんを対象に、血液中に存在する第VII因子(凝固反応を司るたんぱく質の一種)製剤を静脈投与することで、後遺症の軽減を図る無作為化比較試験を計画しました。本研究はアメリカ国立衛生研究所(NIH)、日本医療研究開発機構(AMED)より助成を受け、厚生労働省に先進医療として承認を受けたうえで実施します。(https://fastest.stroke-ncvc.jp/index.html) |
6. T-FLAVOR研究
| 公式名称 | 新規血栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再灌流療法への臨床応用を目指した研究 Tenecteplase versus alteplase For LArge Vessel Occlusion Recanalization ; T-FLAVOR |
|---|---|
| 主任研究者 | 豊田 一則 (共同代表 杏林大学 平野 照之) |
| 事務局 | 井上 学、田中 寛大 |
| 研究内容のご紹介 | 欧米豪ではテネクテプラーゼと呼ばれる新たな血栓溶解薬が、治療ガイドラインでも推奨され、患者さんへの使用例も増えてきました。このテネクテプラーゼは、国内で未承認・未発売です。日本脳卒中学会の血栓溶解薬プロジェクトチームが、国内への早期導入を行政や製薬企業に働きかけてきましたが、目立った進展は見られませんでした。そこで、局面打開のために、医師主導の臨床試験を立ち上げる必要性が求められ、T-FLAVOR試験を始めました。 T-FLAVOR試験は、日本医療研究開発機構(AMED)の助成を受け、また厚生労働省が認めた先進医療として、国内14施設が参加して行われています。 |
7. I-IDIS研究
| 公式名称 | International Intracranial Dissection Study |
|---|---|
| 主任研究者 | 古賀 政利 |
| 事務局 | 三輪 佳織、吉村 壮平 |
| 研究内容のご紹介 | 頭蓋内動脈解離は、若年脳卒中の重要な原因の一つであり、脳梗塞やくも膜下出血の原因になります。日常診療で精密なMRI検査を行えるようになり、非侵襲的に頭蓋内動脈解離を診断できることが増えています。これまで東アジアから頭蓋内動脈解離の報告が多く、人種差の存在が疑われています。スイスのベルン大学、バーセル大学と共同で欧州諸国と日本から500例の頭蓋内動脈解離例を登録して1年間のフォローアップを行っています。観察研究結果をもとに、抗血栓療法の介入試験などを検討する予定です。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02756091 |
8. ELAN試験
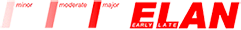
| 公式名称 | Early versus Late initiation of direct oral Anticoagulants in post-ischaemic stroke patients with atrial fibrillatioN |
|---|---|
| 研究代表者 | 古賀 政利 |
| 事務局 | 井上 学、吉村 壮平、田中 寛大 |
| 研究内容のご紹介 | 非弁膜症性心房細動が原因で起こる脳梗塞の二次予防に新規経口抗凝固薬(DOAC)を使用することが一般的になりました。しかし、脳梗塞発症後早期は脳梗塞再発とともに出血性梗塞なども起こりやすいタイミングであり、適切なDOACの開始時期が明らかになっていません。そこで、欧州諸国と共同で2000例を目標に脳梗塞の大きさ別に発症後早期のDOAC開始(48時間以内〜6日)とこれまで行ってきた通常DOAC開始(3日〜12日)を無作為割付で比較する試験を行い、脳梗塞発症後のイベントを比較しています。 https://www.elan-trial.ch/about-the-trial/ |
9. Open GeneS
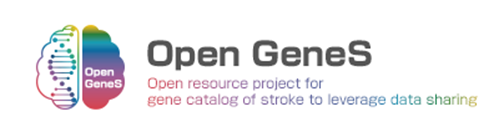
| 公式名称 | 研究利活用のための脳卒中病態解明に資するゲノムデータベースの構築 |
|---|---|
| 研究代表者 | 古賀 政利 |
| 事務局 | 三輪 佳織、吉村 壮平 |
| 研究内容のご紹介 | 脳卒中は重要な国民病であり、ゲノム情報に基づく個別医療の実現が期待されています。脳卒中の大半は多因子疾患であり、ゲノム研究には大規模な症例数が必要です。本研究は、効率的な脳卒中ゲノム研究を実施する推進力となるべく、国内の脳卒中ゲノム研究を集約し、情報化を行っています。 脳卒中ゲノム研究データベースは公開しており、利活用により、ゲノム研究の発展が期待されます。本研究は日本医療研究開発機構(AMED)より助成を受け、開始しました。 (https://o-genes.sbcs.jp/registry_list.html) |
10. 日本脳卒中データバンク
| 公式名称 | 多施設脳卒中レジストリ「脳卒中データバンク(Japan Stroke Data Bank: JSDB)」を用いた我が国の脳卒中医療の研究 |
|---|---|
| 研究責任者 | 豊田 一則 |
| 事務局 | 古賀政利、吉村壮平、三輪佳織、吉江智秀 |
| 研究内容のご紹介 | 日本脳卒中データバンク(JSDB)は、全国規模で脳卒中患者に関する詳細な臨床情報を収集・解析することにより、脳卒中医療の質の向上とエビデンスの構築に寄与することを目的とした、わが国を代表するデータベース事業です。2015年より国循脳血管内科での運営を行っておりますが、前身にあたる「Japan Standard Stroke Registration Study(JSSRS)」(主任研究者:小林祥泰先生)、公益社団法人日本脳卒中協会の「脳卒中データバンク部門」としての運営を合わせると、1999年から25年間、30万例の症例集積があります。約5年おきに書籍刊行も行い、来年には5冊目のテキスト「脳卒中データバンク2026」の発刊を計画しています。(https://strokedatabank.ncvc.go.jp/) 日本脳卒中協会の季刊誌JSA Newsに掲載されている脳卒中データバンク関連のニュースもご参照ください。<日本脳卒中協会 会報 – 公益社団法人 日本脳卒中協会> |
3.当科が最近主宰した医学会
1. 日本神経学会第114回近畿地方会
| 会長 | 会長:豊田一則 |
|---|---|
| 会期 | 2019年7月27日 |
| 会場 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)(大阪市) |
| 学会HP | https://www.neurology-jp.org/sokaitiho/kinki.html |
2.第8回日本心血管脳卒中学会学術集会
| 会長 | 会長:豊田一則 |
|---|---|
| 会期 | 2021年4月17日 |
| 会場 | 国立循環器病研究センター講堂(大阪) |
| 学会HP | https://cvss2021.stroke-ncvc.jp/ |
3.第10回韓日合同脳卒中カンファレンス(10th Korea-Japan Joint Stroke Conference)
| 会長 | 豊田一則(国立循環器病研究センター 副院長) |
|---|---|
| 会期 | ライブ:2022年9月17日(土)~ 9月18日(日) |
| 会場 | Web参加形式。なんばスカイオコンベンションホールから中継 |
| 学会HP | https://www.c-linkage.co.jp/kjjsc2022/ |
4.第42回日本脳卒中学会学術集会(STROKE 2025)
| 会長 | 豊田一則※運営委員長 |
|---|---|
| 会期 | 2025年3月6日~3月8日 |
| 会場 | 大阪国際会議場(大阪市) |
| 学会HP |
4. 当科の業績
5.臨床研究
急性期脳血管障害の新しい診断・治療技術の開発、脳卒中急性期診療に関する全国多施設共同研究、慢性期の再発予防対策、一次予防対策などに関して、活発な調査・研究活動を行っています。再生医療などの新しい治療法の開発にも、取り組んでいます。
6.卒後研修
超急性期脳梗塞への静注血栓溶解療法や脳卒中ケアユニット整備など脳卒中診療を取り巻くわが国の環境は大幅に改善されつつありますが、その診療を支える人材は圧倒的に不足しています。当科では、脳卒中に対する急性期および慢性期実地診療、医育機関における臨床研究や教育を支える人材を育成することを目的に、専門修練医やレジデントを積極的に受け入れ、研修指導しています。わが国における最先端の脳卒中の診療技術の習得に加えて、広く心臓疾患、脳神経外科疾患、腎臓・高血圧疾患、内分泌代謝疾患、救急疾患、リハビリテーション医学を含めた領域の知識の習得と実地研修を行うカリキュラムを、組んでいます。さらに前向き臨床研究や臨床治験に参加し、学会や医学雑誌を介して国内・国外に情報発信を行えるように指導を行っています。
最終更新日:2025年12月25日
