臨床工学部
診療科等の概要
臨床工学部の概略
臨床工学部は、医療機器に関わる専門家として『医療機器の操作及び保守』、『安全使用のための環境整備』および『高難度新規医療技術』に対応している。手術室での人工心肺を使用した心臓血管外科手術、集中治療部での補助循環装置や血液浄化療法及び人工呼吸療法、心カテ室でのABL治療/インターベンション治療、心臓移植部門での補助人工心臓による重症心不全治療などに貢献している。臨床研究などにおいても医師主導治験などにも積極的に参画、自己研鑽としては学会発表や専門/認定士取得、最新の医療知識/技術の習得に努めている。
※臨床工学技士とは、【Clinical Engineer(CE):(国家資格)】
医師の指示の下、人工心肺装置/血液浄化装置/人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者。医学的、工学的な知識を有する専門技術者。
臨床工学部の運営
臨床工学部長/技士長の下、副技士長/主任を置き各領域の人員配置及び調整を行っている。部の運営については、『主任会議』で業務提案・改善などを取り纏め審議、部内に周知徹底する。日々の業務においては、マネジャーを配置し円滑な業務の采配を行っている。

(臨床工学技士室)
スタッフ紹介
臨床工学部の構成
前田琢磨:【麻酔(手術)部長、臨床工学部長】
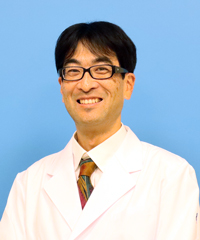
井上裕之:【臨床工学技士長】
髙橋裕三:【副臨床工学技士長】
西岡宏、小川浩司、近藤智勇:【主任臨床工学技士】
臨床工学技士24名
研究補助員1名
外部委託スタッフ3名 【総勢34名】
【認定資格】
| 認定資格 |
|---|
| 体外循環技術認定士 |
| 人工心臓管理技術認定士 |
| 不整脈治療関連専門臨床工学技士 |
| 植込み型心臓デバイス認定士 |
| 心血管インターベンション技師 |
| 呼吸療法認定士 |
| 透析技術認定士 |
| ME専門認定士 |
| 特定高圧ガス取扱主任者(酸素) |
最終更新日:2023年07月18日
