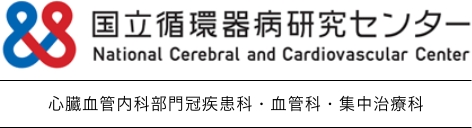柳生 剛
YAGYU TAKESHI
【専門領域】
下肢動脈カテーテル治療(EVT)
遺伝性動脈疾患

診断と治療までに関われる魅力に惹かれ
循環器内科へ
医師としての最初の2年間のローテーションでさまざまな診療科を経験しましたが、その中でも、多くのシチュエーションにおいて、診断から治療までを自身で完結できる循環器内科に大きな魅力を感じました。循環器内科は忙しい診療科というイメージもあるようですが、私自身その点においてはまったく躊躇することはなく、冠動脈疾患の治療以外にも、不整脈、心筋症など多岐にわたって学ぶべきことがあり、そのひとつひとつを習得していくモチベーションや意欲のほうが勝っていました。むしろ「できないことができるようになる」というプロセスを楽しく感じていました。
日本のスタンダードを学ぶために
国立循環器病研究センターへ
患者さんの治る過程を
サポートするのが医師の役目
国立循環器病研究センターで働き始めてから、診断のプロセスにはじまり、今まで経験することが少なかった不整脈や重症心不全の患者さんの対応なども経験することができ、今まで私の中になかった治療の選択肢を増やすことができました。このように治療の選択肢を多く持てることは、患者さんにとってはもちろんのこと、医師にとっても良いことだと思います。
冠動脈インターベンション、心不全治療など心疾患における治療の経験を多く積むことができ、現在は血管病変を主に担当する血管科に身を置いています。そこで行う末梢血管のインターベンションは、デバイス(機器)の発展も早く、毎年のように新しいものが出てくるため、日々ブラッシュアップしなければいけません。2~3年前にはスタンダードだった治療が行われなくなることも多いですので、治療の難しさとあわせて、新しいことを学び身につける日々の努力が求められますが、非常にやりがいがある分野だと感じています。
様々な症例を経験する中で私が大切にするようになったことは、内科医の主な役割とは患者さんが治る過程を手助けすることであるということです。つまり治療の中心はあくまで患者さんです。当然のように聞こえるかもしれませんが、医師がどれだけ頑張っても、患者さん自身に治すという意思をもって頂かないと、結果が伴わないことはよくあります。例えば、血管病変においては喫煙が良くない影響を与えるのは常識ですので、患者さんが「喫煙を続けながら治療を受ける」という状況は非常に好ましくありません。当然、まず禁煙していただいた上で治療に進むわけですが、患者さんによっては中々ご理解頂けないこともあります。このような時に、頭ごなしに否定するのではなく、患者さんに理解して頂けるよう働きかけ、患者さん自身が主体的に治療に取り組むことを促すようにしています。
国立循環器病研究センターだからこそ携われる希少な研究テーマに挑む
現在、マルファン症候群やエーラスダンロス症候群といった遺伝性血管疾患の診療と研究にも取り組んでいます。
これらの疾患は頻度が低く、それ故まだまだ正確に診断されていないケースがあるように思います。ですので、まずはしっかりとした診断がなされる環境から整える必要があります。
今は日本人のデータをしっかりと集めるという、本当に足場を固めるところから取り組んでいます。次に、日々進歩している遺伝学的検査の技術を積極的に取り入れ、診断の精度を今以上に上げていきたいと思っています。また、一般的には遺伝子検査はハードルが高い検査となるため、バイオマーカーによる診断、つまりは血液検査によって診断や病気の進行具合などが把握できるようにしたいとも考えています。
診断における研究成果が出れば、治療に結び付くような成果も望まれますが、実現するにはいくつも高いハードルを越えなければいけません。非常に長い道のりだとは思いますが、このような希少な疾患の診療や研究に集中的に取り掛かれるのも国立循環器病研究センターだからこそと思います。遺伝性の血管疾患に対応できる専門的施設は国内も非常に少ない状態ですので、関西にお住まいの患者さんであればまだ当院を頼ることができたとしても、それ以外の地区でお近くに専門病院がなく困っている患者さんもたくさんいらっしゃると思います。そのような方々の力になることができればとも思っています。
救急の要となる循環器内科を学ぶ意義
津々浦々から集まったプロフェッショナルから学べる環境
循環器内科というと救急診療やカテーテルインターベンションというイメージが強いと思います。私自身も若い頃はまず救急の場で成果を出せる医師にならなければいけないと思っていました。救急において循環器疾患は非常に重要な領域ですので、その点だけにおいても循環器内科を学ぶことは非常に意義があることだと思います。
更に、循環器内科では、救急外来の超急性期だけでなく慢性期に至るまで幅広いシチュエーションに関わることにもなります。治療技術の研鑽はもちろんのこと、臨床研究のような頭を使う取り組み、新しいデバイスの勉強など、本当に幅が広いアプローチ方法があります。
国立循環器病研究センターは、臨床はもちろん研究の分野においても日本の第一線で取り組んでいるため、循環器内科を極めたいと考えている医師にとってよいトレーニングの場になると思います。臨床での一例をいうと、日本中から医師が集まっていますので、その出身地域やもともと在籍していた病院など、それぞれのバックグランドによってカテーテルの扱い方や考え方などが微妙に異なります。そのため新しく来られた人の中には、これまで習得した技術や考え方と異なる指導を受けることもあり得ます。一見すると混乱をきたしてしまいそうにも思いますが、いいところだけ取り入れて自分流に技術を磨いていくことができるという考えに立てばメリットが多いと思います。
次に臨床研究においては、やはり症例数のアドバンテージが大きいと思います。臨床研究を進めるには、何百、何千という症例データが必要になりますし、数が集まらないと価値のある結果を生み出すことができません。ひとつの施設での研究、多施設での共同研究、どちらの場合においても、国立循環器病研究センターのように研究の中心となれるような施設でないと十分な症例数を確保することが難しいという現実があります。研究で成果を出すためには、身を置く環境も非常に大切になりますので、その点においても国立循環器病研究センターは魅力的な病院であると思っています。
Doctor Profile
柳生 剛
YAGYU TAKESHI
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)認定医
心臓リハビリテーション指導士
脈管専門医
その他疾患や実績については以下よりご確認ください。
その他病態

Acsess
〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号
医療機関の皆様へ
虚血性心疾患の検査として、近年ではマルチスライスCT検査での冠動脈評価の精度が向上し、外来で冠動脈の解剖学的な評価が可能になりました。
※緊急受診について
以下のような症状が出ている場合は緊急にかかりつけ医を受診ください。
-
医師から処方されている(ニトログリセリンなどの)舌下錠を3回舌下しても症状があるとき発作が頻回に起こるようになってきたとき
- 医師から処方されている(ニトログリセリンなどの)舌下錠を使うと症状が良くなるが、すぐに症状がでてくるとき
- 夜中に苦しくなって目が覚めるようになったとき
- 急に体重が増えたとき
※夜中でも「朝まで・・・」と我慢する必要はありません。
※外来の日が近くても、上記のような症状があったら、すぐにかかりつけの病院に連絡して下さい。